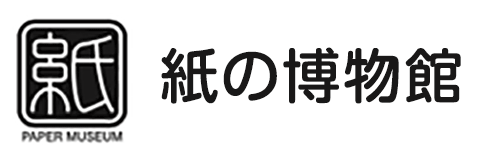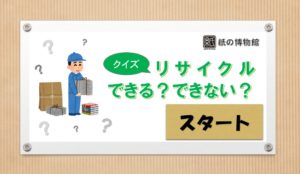遠くて紙の博物館に来られない人や、おうちですごす時間が長い人のために、 紙の工作やおすすめの本、クイズなどをごしょうかいします。 おうちでも、博物館を楽しもう!
保護者の皆様へ
「おうちミュージアム」は、「子どもたちがおうちでミュージアムを楽しめるように」との趣旨で北海道博物館が発案した企画です。この趣旨に賛同し、当館でも「おうちミュージアム」を実施します。お子さまといっしょにお楽しみいただければ幸いです。
紙のQ&A
今まで博物館に寄せられた質問をまとめました。 →こちらをクリックしてください
おもちゃ絵であそんでみよう
「おもちゃ絵」は、子ども用に作られた浮世絵で、見て楽しむだけでなく、切ったり、はったり、工作して楽しむものなどいろんな種類がありました。江戸~大正期の子どもたちのように、おもちゃ絵を楽しんでみましょう。
おもちゃ絵(1) 変わり絵
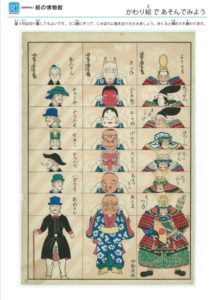
(変わり絵)歌川芳虎画/伊勢辰版
タテ3列に「外国人」、「お面」、「武者」が描かれ、それぞれ色々な顔が7段分ある「変わり絵」です。タテ3列は切りはなしてもよいです。じゃばらに紙をおりたたんでめくると、顔が入れ替わります。自分でオリジナルの変わり絵も作ってみるのも、おもしろいですね。
左「外国人」上より
なんきん/おろしや/ふらんす/とるこ/おらんだ/いぎりす/あめりか
中「お面」上より
きつね/金太郎/おかめ/げどう/大てんぐ/ひよつとこ/あくま
右「武者」上より
よりとも/巴ごぜん/まさしげ/けんしん/しんげん/ただのり/よしつね
おもちゃ絵(2) 着せ替え絵
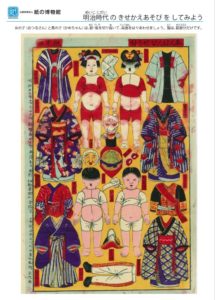
「しんぱんいせう付」歌川国利画/越米版/明治27年(1894)
明治時代のきせかえあそびをしてみませんか?
女の子(おつるさん)と男の子(かめちゃん)は、前・後を切り抜いて、両面をはりあわせましょう。服は、前部分だけです。切り抜いて、いろいろきせかえてみましょう。ぼうしやお面などの小物もあります。
オリジナルすごろくをつくってみよう
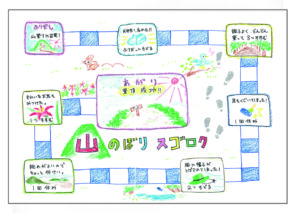
①すごろくのテーマを決めて、「ふりだし」と「あがり」の位置を決めます。「山のぼり」「おやつ」「買い物」など、身の回りの事柄をテーマにしてみるのもいいですね!
②ふりだしから上がりまで、すきな数だけマス目を作って、つなぎます。その中に、「3つ進む」「1回休み」「ふりだしにもどる」などのおもしろい動きをするマスをいくつか作ります。嬉しいイベントや、思わぬハプニングは、すごろくの世界を広げてくれますよ。
③テーマにそって、絵を書いたり、色をつけます。
④遊びたい人数分のコマを作って、完成。サイコロを準備して、みんなで遊びましょう!
紙についての本のリスト
図書室から、自由研究やおうち学習に役立つ本のリストをおとどけします。
◇おすすめ児童書リスト(PDF175KB)2023/7/9 更新・掲載
紙について学べる児童書を一覧にしました。
◇自由研究おすすめ図書・情報(PDF134KB)2024/7/12 掲載
2024年夏の企画展「「紙」の自由研究」にあわせて作成したものです。
[過去リスト:自由研究おすすめ図書・情報(PDF132KB)2023/7/9 掲載]
◇テーマ別 児童書リスト
1)紙を知ろう! (PDF 112 KB) 2024/7/12更新・掲載
紙について学びたい方に是非読んでほしい児童書リストです。
2)和紙について (PDF 110KB) 2024/7/12更新・掲載
和紙について学べる児童書リストです。
3)紙をつくろう! (PDF 111KB) 2023/7/14 更新・掲載
紙の作り方が紹介されている児童書リストです。
4)紙と環境問題 (PDF 119KB) 2023/7/14 更新・掲載
環境問題やリサイクルについて学べる児童書リストです。
5)段ボールについて (PDF 112KB) 2023/7/14 更新・掲載
段ボールについて説明がある児童書リストです。
紙の博物館の図書室では、本を読むことができます。図書室のページはこちら。
ぬりえ